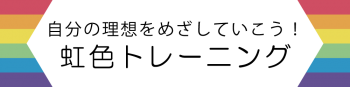■真面目な人ほど危険

アスリートが注意しなければいけないことの一つにオーバートレーニング症候群が挙げられます。
現在のようにコロナの影響で試合が出来なかったりしていると、トレーニングに打ち込む選手も多いでしょう。
目標が設定できないままトレーニングに打ち込んでいても、結果というものが付いて来ません。
ですが、先が見えない不安感からも、トレーニングを続けてしまう可能性は十分に考えられます。
本来であれば、一定のトレーニングの後には、体を休ませなければいけません。
これが体を育てる大事なポイントにもつながりますが、その余裕もなくしてしまう可能性があるのです。
ここで危惧しなければいけないのが、オーバートレーニング症候群であるのは周知の事実となりました。
オーバートレーニング症候群は、真面目な人ほど起こりやすい状態です。
トレーニング不足なのかと思い込んでしまうことが、体のリミットを超えたトレーニングに発展させてしまう可能性が出てきます。
徐々に疲労感が抜けなくなり、日常生活にも支障が現れてくればかなりの問題です。
パフォーマンスの低下だけではなく、数日休んだだけでは、疲労感抜けません。
貧血などの症状も引き起こし始めますが、病気が原因であったりはしないのです。
このような状態はオーバートレーニング症候群と診断される状態で、自律神経の異常も伴ってしまうかもしれません。
様々な異常が見られるのも特徴で、不眠やうつ症状を訴える場合も出てきます。

オーバートレーニング症候群の難しいところは、このような症状が現れれば危険だと言った定義がはっきりとしてません。
総合的な部分で判断していかなければいけないからです。
更なる問題点として、回復させるためにも長期の時間が必要であり、焦って悪化させるでも少なくありません。
体調を見ながらトレーニングを進めていかなければいけませんが、本人には強い焦りが生まれてきます。
その葛藤の中で、徐々にトレーニングを増やすなどの対処をしなければいけないのです。
アスリートにとって、トレーニングは絶対不可欠の要素であるのは確かです。
結果を出すために様々なトレーニングを繰り返して行きますが、常に客観視した状態確認が必要と言えるでしょう。
自分自身の主観だけでトレーニングを続けていると、無理が祟ってしまうのも当然です。
いつ辞めていいのか、いつまでしなければいけないのか、科学的な判断も必要といえます。
専門的な知識が活用される場面ともなるため、オーバートレーニング症候群にならないような計画が必要な時代なのです。