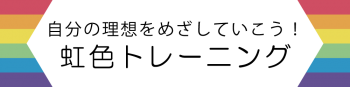■体重差によって大きな違いが生まれる

年末になると格闘技のイベントもさまざまなものが行われます。
この時期を楽しみにしている人も多いでしょう。
イベントを見てコンタクトスポーツを始めようと思う人も出てくるはずです。
そこで注目しておかなければいけないのは、なぜそこまで階級差があるのかというポイントになります。
競技によっても体重の分け方が違いますが、決められた体重の範囲に合わせて体を作らなければいけません。
ボクシングなどでは契約ウェイトという方法もあり、階級の枠組みを超えてお互いで納得した体重で試合をする場合もあります。
格闘技の中で階級という意味で厳格なボクシングで見てみると、男子では階級が17種類、女子では18種類に分けられるようになりました。
団体によって違いが出てくる場合もありますが、おおよそこの数の中に収まると考えて間違いありません。

体重によってクラスを分けるのは、体格差をある程度の範囲に収める意味があります。
体の大きな人と小さな人が戦うと、リーチの差などもあり大きなハンデになるのは間違いありません。
体重を増やせることにより、筋肉量が増加します。
これによりパワーの差が出てくるため、選手自身を守るためにも階級が作られました。
記憶に新しいところでは、2018年のルイス・ネリ対山中慎介のWBCバンタム級タイトルマッチがありました。
前日計量で5ポンドオーバーを記録し、再軽量しても3ポンドオーバーの状態だったのです。
3ポンドですので1.36㎏オーバーでした。
単純に1.3㎏と考えるかもしれませんが、ボクサー達の体脂肪率は極端に低く、これだけの筋肉量の差がつくと考えなければいけません。
実際に無理な減量をしていなかったため、筋肉をしっかりと付いていました。
つまり、著しくパワーの差が生まれてしまうのです。
これだけの体重差は危険だと言う意見が多い中、試合が行われました。
結果としては、山中選手の衝撃的なダウンシーンで幕を閉じるのです。

トレーニングとして考えても、体重はとても大切です。
どの体重を適正とするのかを見極めながら、本番に合わせて体を絞り込まなければいけません。
特にコンタクトスポーツの場合には、絞り込んだ体重はパワーに直結します。
体脂肪率もギリギリまで落としてくるため、わずか数百グラムの差でも違いが出ると言えるでしょう。
だからこそ、常に計画的なトレーニングが必要であり、その中で怪我などをしてパフォーマンスが発揮できない状態を作らないことが大切です。