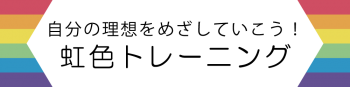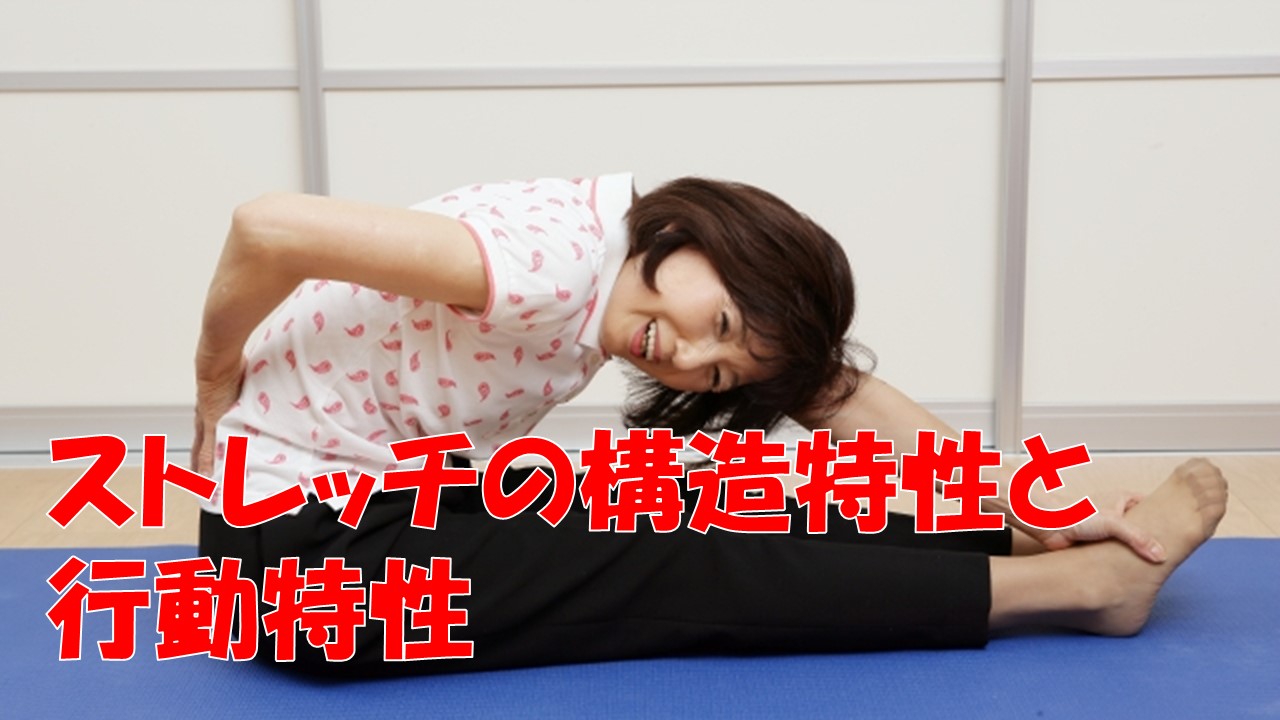通常のストレッチは、シンプルなものが中心です。
関節が曲げられるところまで動かし、筋肉が伸びるところまで引き延ばすというのがこれまでの考え方でした。
確かに理にかなった方法であり、基本的な動きとしては間違いありません。
しかし、人間の体の筋肉は、そこまで簡単な構造ではないのです。
ただ伸ばしたりするだけでは、十分にストレッチができたとは言えないことがあります。
スポーツのパフォーマンスを向上させたりするためには、筋肉の構造や特性を理解してストレッチしていかなければいけません。
効率を高めるためにも知識が必要なのです。

基本となるのは構造特性です。
一体どこを伸ばしたいのか、ここから考えなければいけません。
筋肉は、様々な動きをしていきます。
以前であれば、トレーニングは背筋を伸ばして行うものと考えていたでしょう。
例えば、広背筋を伸ばすとしたら、背筋を伸ばしていては効果がありません。
伸ばすためには腕と肩を前に出したまま背中を丸めなければいけないのです。
これが目的に応じたストレッチであり、構造特性を理解しなければできない点と言っていいでしょう。
行動特性のポイントとして、腕と足の付け根に関しては多方向に伸ばさなければ意味がないことがあげられます。
球関節を持っているためで、非常に大きく動くような扇形の構造を持つ筋肉だからです。
そのため、部分的にストレッチが効く方向があるため、広く多方向に伸ばしていかなければ効果をあげられません。
ただ筋肉を引っ張るだけではなく、ゆるめることでのばせる筋肉が出てくる場合もあります。
こうした筋肉の行動特性を理解した上でストレッチをしなければいけないのです。

ストレッチを効率的に行うためには、てこの原理も利用してきます。
単純に伸ばそうとするだけではなく、てこが長くなるように意識することで、少ない力でストレッチができるからです。
力を強くかけなくて済むため、怪我をしたりする危険性も少なくなります。
同じ力でも効率的にストレッチができるようになるので、楽にできるようになるでしょう。
窮屈な姿勢で行わないことも大切です。
どんなトレーニングでも、窮屈な姿勢で続けていればストレスがかかります。
精神的にもリラックスできない状態が出来上がり、効率を落ちてしまうのです。
スポーツのパフォーマンスを高めるためにするのであれば、楽な姿勢を取りゆっくりとした動きでストレッチしていくことが求められます。